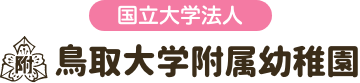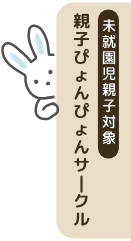研究について
令和7年度公開研究会
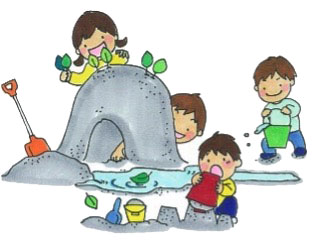
本園は、創立以来大切にしてきた子どもたちの主体性と「遊びは学び」であるという基本をもとに、さらなる保育と研究実践の充実をめざしています。今年度は、テーマを『「やってみたい」を支える保育』として、研究を進めています。
さて、10月18日(土)に公開研究会を開催しました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。保育公開を行い、のびのびと遊ぶ子どもたちの姿を参観していただきました。分科会では、子どもたちの具体的な姿や保育者の援助について、熱心に協議をしていただき充実した会となりました。講演会では、上月智晴先生(京都女子大学発達教育学部准教授)に、「幼児期の運動あそびで大切にしたいこと~すべての子どもに運動の喜びを~」と題して、保育における運動あそびの重要性や保育者の援助で大事なこと等について、様々な資料や映像を用いて大変分かりやすくお話していただきました。
公開研究会の様子
公開保育






参加者の感想
- 環境構成で参考にしたいところがたくさんあった。
- 保育者のかかわりや環境の準備のもと、子どもたちが試したり主体的に活動したりする姿が多く見られた。
- 子どもたちが「やってみたい」という気持ちをもてるような先生方の声掛け、援助、また、環境の構成の仕方等自園でも取り入れていきたい。
- 先生方の子どもたち一人ひとりに関わる声かけや動きなど、学ぶ事がたくさんあった。ちょっぴり支援を必要とする子どもへのかかわりも、子どもに寄り添って促したり、待ったりと、時間が穏やかに過ぎているように感じた。
- 子どもの遊びの様子、取り組み、園児数規模が似ており、自園の保育も振り返りながら見させてもらった。
- 子どもの気になる行動を注意するのではなく、気づきを促すような言葉かけをされ、子ども自身が気づき、行動を自分でなおせるように配慮されていた。
- 保育者と園児のリアルな関わりを見て、園児との接し方や園内の環境などについて学ぶことができた。
- 保育を見させていただく中、どの先生方も全クラスの子ども達のことを把握して関わっておられることがすごく感じられた。
- どの遊びの中でも子ども達の意思を尊重する声掛けや自ら考えやってみようと思える声掛け、しかけ、いいなぁと感じた。
全体会


参加者の感想
- 保育の意図や、日々、先生方が取り組まれていることを具体的に知ることができた。
- テーマに沿って、園全体でじっくり子どもたちと向き合いながら保育を進めておられることがよく伝わり、自分の園でも実践したいと思う内容が多々あった。
- 遊びから運動会の種目に繋げているのが印象的だった。子どもたちの興味や「やってみたい」からその後の遊び、行事へと広げていくことが大切だと実感できた。
- フォトエピソード、ミニフォトトークは、参考になった。保育士の語り合える場を設ける事でより子ども理解が深まり、共有する事ができると感じた。
- 遊びが発展していく時の子どもの様子や、先生方の援助、環境構成の工夫を知ることができてとても学びになった。
- 職員間の連携と対話をもとに、子どもの実態を分析し、日頃の保育に活かしていることが分かった。
- これまでの保育の流れも、分かりやすく発表されて良かった。
- 研究の取り組みやこれまでの経過がよくわかった。
分科会


参加者の感想
- 現職の保育士の方の話を聞くことができた。附属幼稚園だけでなく、他の保育園での実践もふまえながら考察をすることができて、とても貴重な体験になった。
- 各グループで話し合い、発表の後に、もう一度グループで話し合いができたら、より実りがあるものになったように思う。
- 行政の方、学生さんと一緒のグループで、色々な視点での意見交換ができ刺激をいただけた。
- 同じ場面を見た他の参加者と話ができ、自分の考えを深めることに繋がった。また、他のグループの発表を聞くことも学びになった。
- 実際の保育経験も踏まえてグループで話し合う中で、本日の公開保育で子どもたちの「やってみたい」を支える支援の仕方や環境についていろんな立場の職員で話せたことで気づきが多かった。
- お互いに悩むところが同じ部分であったり、日々悩み考えながら保育をしたりしていることなどを共感しあえる時間となり、明日からの保育も頑張ろうという気持ちももてた。
- 子どもの姿や保育の振り返りを自分以外の人と共有する面白さや、お互いに共感し合える楽しさ嬉しさ、子どもをより深く理解していく大切さを、分科会の話し合いを通してあらためて感じた。
- 自分が気づかなかった他の方々の視点を学ぶことができとても参考になった。
- 公開保育で同じ場面を見ていたとしても違う気づきがあり、新たな発見をすることができた。
講演会


参加者の感想
- 幼児期の運動という視点から、改めて私たちに何ができるかを考えさせられました。視点を変えると、また違ったものが見えてくることが面白かった。
- 幼児期における運動遊びの大切さが、幼児期前半・後半と具体的にわかりやすく教えていただいた。具体的な事例もよかった。できる、できないではなく、身体を動かすことが心地よい、楽しいという経験を一緒に積んでいきたいと思った。
- まずは子どもたちが「楽しい」と思える活動を考えることの大切さに気づくことができた。
- 運動が、できる!できない!ではなく、共に育ち合う喜び、学び合う喜びが大切だと改めて感じた。
- 今のクラスの子ども達の姿が浮かび、保育を展開する上での大きなヒントを頂いたと感じた。
- 生活全般が昔の時代に比べ便利になっているからこその、より意識的な運動の取り組みが必要ということを聞きとても実感できた。
- 楽しい雰囲気の中、やってみようという気持ちをもって挑戦できる保育の工夫をしていくことが大切ということを改めて感じた。
- 幼児期に大切な自己肯定感についても、幼児期の外遊びの経験が大きく影響していることなども知ることができた。
- 運動遊びの大切さを十分理解できたとともに、実践事例や動画は、考えさせられたり感動したりで大変有意義な講演だった。
- 理論も大切だが、その場の楽しい雰囲気やムードづくりで子どものやってみたい気持ちが変化することにも気付かされた。
- 幼児期の運動遊びの大切さを学べたとともに、雲梯や竹馬、リレー等、具体的な例から運動遊びの奥深さを知ることができた。