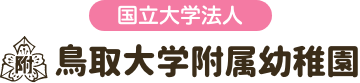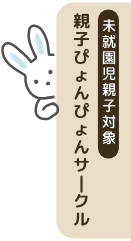研究について
研究の概要
令和7年度の研究テーマ
研究主題
「やってみたい」を支える保育
研究主題設定の理由
本園は、幼児期の子どもにとって「遊びは学びである」という考えの基に保育を行っている。そして、子どもが自ら遊びを見つけ、試行錯誤し、主体的・協同的に遊びを深める中で様々な経験をすることを中心に据えて保育を行っている。人やモノ、コトとの関わりをもちながら、様々な心が動く体験を通して遊びは充実していき、好奇心や探究心、気付き、工夫などをはじめ多くの学びが生まれると考えている。
令和4年度から6年度は、「子どもが夢中になって遊ぶ保育」を目指して、研究に取り組んできた。職員研修の充実を図り、具体的な子どもの遊ぶ姿を取り上げながら幼児一人一人の思いや実態に目を向けて、環境構成を含めた保育者の援助の在り方を中心に新たな話し合い(フォトトーク)を行った。友だちとの関わりに重点を置き、遊びを深めていくための保育者の援助についても模索した。遊びが深まった場面での子どもの思考の流れを、友だちとのつながりや保育者の援助とともに時間の経過が分かるように記録(フォトエピソード記録)した。この記録を通して、保育者は子どもの思考の流れを大切にして丁寧に見取ることで、遊びのつながりを今まで以上に意識するようになり、長期間の保育の見通しをもちやすくなった。子どもたちは、友だちと動作や表情、言葉などのやりとりをしながら関わり合い、達成感や満足感を感じながら遊ぶ様子が、今まで以上に見られるようになった。さらに、遊びの途中で援助に悩んだとき等に他の保育者の考えを聞き、もっと保育を充実させたいという思いから、「次の保育につながる 環境の再構成」ということに重点を置き、子どもが夢中になって遊ぶ姿を目指した。カンファレンスの内容を踏まえて「環境の再構成」を行うことで「保育者の援助」を充実させて次の保育につなげていった。
これまでの研究の成果を踏まえ、本年度の研究を進めるにあたって、改めて、本園の子どもたちの実態について話し合った。よさとしては、「好奇心や興味をもって遊ぶ」「素直にがんばる」「異年齢を含む友だちとの関わり」などが出てきた。また、遊びを見つけて楽しむ「自主性」や「友だちとの関わりの中での伝え合う力」なども挙げられた。しかし、この「自主性」や「友だちに伝える力」「関わり方(思いやり)」などは、課題の方でも似たような内容が出てきた。特に、経験の少ない活動に対して不安を感じる姿や、自信のなさから自分のしたい遊びが伝えられなかったり、踏み出せずにいたりする姿が挙げられた。こうした傾向から、自分たちで遊びを選んで取り組む本園の保育のよさを生かしつつ、さらに興味を広げていく姿へと繋げていきたいと話し合った。そのために、子どもの「やってみたい」という気持ちを起点に、安心して活動に踏み出せるような援助や環境構成のあり方を考えることが、今後の保育の質を高める上で重要であると考えた。
そこで本年度は、子どもが興味や関心をもち、「やってみたい」という思いからスタートすることで、遊びが発展していく保育について研究していきたいと考えた。研究にあたっては、昨年度まで取り組んできたフォトトークを、「ミニフォトトーク」という形でも行うことにし、保育者同士のカンファレンスの機会を増やしていく。子どもたちが今取り組んでいる遊びや、興味関心を共有することで、保育者一人一人が幼児理解を深め、より適切なタイミングで援助できるようにしていきたい。非常勤職員も含めて話し合う場を定期的にもつことで、次の日からの保育の充実に生かしていく。話し合った内容や実践は、フォトエピソード記録にまとめ、職員間で共有していく。子どもの「やってみたい」という思いが、どのように遊びへと繋がり、発展していったのか、思考の流れを丁寧に追いながら、保育者の援助や環境構成の工夫も含めて記録、考察する。
また、令和5年度から実施している運動能力検査を本年度も実施し、日々の見取りや実態把握に生かしていく。子どもの遊びの姿や言動に加え、運動能力検査も分析し評価することで、さらに多面的な視点で保育に生かしたり振り返ったり生かしたりできるのではないかと考える。
また、「担任交換の日(先生となかよしデー)」の取り組みを引き続き行い、子どもの実態把握、発達段階の理解など、保育者同士での学び合いの機会にし、自己研鑽につなげていく。
研究の目的
保育者同士のカンファレンス等を通して幼児理解を深め、「やってみたい」という気持ちを起点とする遊びの展開を意識した援助や環境構成のあり方を探る。
研究の内容
- 保育の振り返り<非常勤職員も可能な範囲で参加>(フォトトーク・ミニフォトトーク)
- 遊びの場面の事例を持ち寄って話し合う。
- 保育者の保育の意図や、環境の構成、援助について話し合う。(カンファレンス)
- 本園の大切にしてきた保育について話題に取り上げ、共通理解を図る。
- 各発達段階で大切にしたい経験や遊び方を共通理解する。
- 実践や評価をまとめた記録を作成(フォトエピソード記録)
- 担任は、子どもの思考の流れが分かるような記録(評価も含む)を作成し、内容を共有する。<各学期に1回>
- 級外は、月のねらい等を意識し、子どもたちの遊びの様子をまとめた保護者向け掲示物を作成する。<1か月を通じて、写真を掲示していく>
- 運動能力検査の実施、分析
- 1回目…5月
- 2回目…1月
- 担任交換による客観的な振り返り<年間4回、1日(登園から降園まで)>(先生となかよしデー)
- 7月、12月…年少(年中担任)、年中(年長担任)、年長(年少担任)
- 10月、1月…年少(年長担任)、年中(年少担任)、年長(年中担任)
- 降園後、話し合い、意見交換をする。
- 教育課程のアップデート
- 教育課程の資料へ加除修正を行う。
- 改訂した月の指導計画の実践、評価(気づいたこと等を朱書きし、来年度へ引き継ぐ)
これまでの研究主題
| 昭和42~43年度 | 指導計画の研究 |
| 昭和44年度 | 指導方法の研究 |
| 昭和45~46年度 | 集団活動の中で創造性をどのように高めたらよいか |
| 昭和47~49年度 | 遊びから遊びを創りだす保育 |
| 昭和50~51年度 | 遊びを通して社会性を育てる |
| 昭和52~53年度 | 豊かな表現活動を育てる |
| 昭和54~58年度 | 社会性を育てる |
| 昭和59~60年度 | 遊びをみつめ意欲的に取り組む子どもを育てる |
| 昭和61~63年度 | 運動遊びを通していきいきとした子どもを育てる |
| 平成元~4年度 | 子どもとともにつくる保育 |
| 平成5~8年度 | 豊かに生きる子どもを育てる保育 |
| 平成9~14年度 | 主体的に生活する子どもを育てる保育 |
| 平成15年度 | 主体的に生活する子どもを育てる保育 ―心をつなぐ遊びと集い― |
| 平成16~18年度 | 育ち合う -保育参加と子育て支援- |
| 平成19~21年度 | 運動的な要素を含む遊びの中の学びとそれを誘発する環境を探る 文部科学省教育研究開発指定校 |
| 平成22~24年度 | 学びをつなぐカリキュラムの創造 |
| 平成25~27年度 | 学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ |
| 平成28年度 | 幼児期の学びをつなぐ―「活動」と「ことば」に着目して― |
| 平成29~30年度 | 「いま伸びする力」と「あと伸びする力」を育てる ~遊びの充実をとおして~ |
| 令和元年~3年度 | 「いま伸びする力」と「あと伸びする力」を育てる ~幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を視点として~ |
| 令和4年度 | 子どもが夢中になって遊ぶ 保育者の援助の在り方 〜職員研修を通して学び合う〜 |
| 令和5年度 | 子どもが夢中になって遊ぶ保育を目指して
~友だちとつながり 遊びを深める~ |
| 令和6年度 | 子どもが夢中になって遊ぶ保育を目指して
~次の保育につながる 環境の再構成~ |